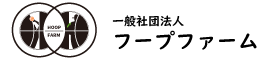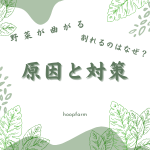家にいるだけで疲れる…その原因は暮らしの“無駄なクセ”かも?
目次
はじめに

「今日は一日家にいただけなのに、なんでこんなに疲れてるんだろう?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実はそれ、心や体の“休まる時間”が暮らしの中にないことが原因かもしれません。
外に出てないからラクなはずなのに、家にいても疲れる――。
それは、自分では気づいていない“無駄なクセ”が積み重なって、エネルギーを消耗している状態なんです。
この記事では、「家にいるだけで疲れる」人によくある生活習慣や思考パターンを見つめ直し、無意識の疲れを手放すヒントをお届けします。
暮らしを少し整えるだけで、家の中はもっと“安心できる場所”になりますよ。
「なんとなくスマホ」が疲労感の元?

家にいる時間、つい手に取ってしまうスマホ。
気づけば何時間もSNSや動画を見ていて、「何もしていないのに、なんか疲れた…」と感じること、ありませんか?
この“なんとなくスマホ”がもたらす疲れの正体は、脳への情報過多と休息不足です。
人間の脳は、目から入ってくる情報を処理するだけでもエネルギーを使います。
特にSNSのように次々と情報が流れるものは、無意識のうちに脳をずっと働かせてしまうんです。
また、スマホを見ているときって、「休んでいるようで休めていない」ことが多いです。
ソファでダラッとしていても、目や指は動きっぱなし、心は情報に振り回されている状態。
これでは、体は止まっていても“脳が休まらない”ため、結果的にどっと疲れてしまうのです。
スマホを見る時間をゼロにする必要はありません。
でも、意識して「○時まではスマホを見ない」「お昼ごはんのあと30分はスマホ断ち」など、小さなルールを決めるだけでも、脳の回復力がまったく違ってきます。
「スマホを置いてぼーっとする時間」こそ、本当に心を癒す時間。
そのちょっとの工夫が、家での疲れをグッと減らしてくれるんです。
「ついで家事」が休息を削っている

休もうと思ってソファに座ったはずなのに、「あ、洗濯物たたまなきゃ」「ちょっと片づけておこう」――
そんなふうに、ふとしたタイミングで家事を始めてしまったことはありませんか?
このような「ついで家事」、実は心と体の休息をじわじわと奪う見えない疲れのもとなんです。
家の中にいると、どうしても目に入るのが“やるべきこと”。
床のゴミ、出しっぱなしのコップ、洗い物…。
「今のうちにやっておこう」とつい動いてしまうのは真面目な人ほど多いですが、これが“休んだつもりなのに休めていない”状態を作り出してしまうのです。
特に、在宅ワークや休日に「ちょっとだけ休もう」と思っているときこそ要注意。
脳と体は、きちんと休息のモードに切り替わらないと回復できません。
そのため、“家にいる=なんとなく働き続けている”という感覚になり、結果的に疲れがどんどんたまってしまいます。
これを防ぐには、「今は休む時間」とあえて決めて、意識的に“何もしない時間”を確保することが大切です。
コーヒーを入れて、お気に入りの音楽をかけて、スマホも手放す。
そんなふうに自分を“休ませるスイッチ”を入れる習慣が、疲れにくい暮らしの第一歩になります。
完璧主義が“無意識のストレス”を生む

「部屋はいつもキレイにしておきたい」
「ご飯はきちんと作らないと」
「生活リズムはちゃんと守らないといけない」――
こんなふうに、“ちゃんとやらなきゃ”がいつの間にか自分を追い詰めていないでしょうか?
実は、完璧を目指す暮らしは、見えないプレッシャーとなって心に負担をかけていることがあるんです。
完璧主義は悪いことではありません。
ただ、その基準が高すぎると、自分を責めるクセに変わってしまうことがあるんです。
「今日は掃除できなかった…私はだらしない」
「また寝坊してしまった…自己管理ができない」
そんなふうに、小さなミスを“自分の価値”と結びつけてしまうと、暮らしがどんどん息苦しくなってしまいます。
また、完璧を求めることで、“やらないと休めない”という心理状態にもなりがちです。
休むことに罪悪感を感じてしまい、結局ずっと動いてしまう…。
これでは、家の中であっても心が休まることはありません。
大切なのは、「まあ、いいか」と思える余白を持つこと。
少し部屋が散らかっていても、冷凍ごはんに頼っても、誰もあなたを責めたりしません。
“暮らしのゆるさ”は、心の健康を守るバリアになります。
完璧を目指すよりも、「今日はここまでできた」と自分にOKを出せる暮らしの方が、ずっとラクに生きられますよ。
「部屋の圧」が心の負担になる

「なんとなく落ち着かない」「家にいるだけでイライラする」――
そんなとき、実は部屋そのものが“ストレスの温床”になっているかもしれません。
床にモノが多くて歩きにくい、目に入るたびに「片づけなきゃ」と思ってしまう。
そんな空間にいると、脳は常に“未処理のタスク”に囲まれている状態になり、気づかぬうちにストレスを感じ続けているのです。
この“部屋の圧”は、自分にしかわからないプレッシャー。
誰かにとっては気にならないものでも、自分にとっては「見たくない」「触れたくない」ものがあるだけで、無意識のうちに疲れが増してしまいます。
また、モノが多い部屋は情報が多い部屋。
脳が絶えず情報処理をしてしまうため、休んでいるようでリラックスできていないことが多いんです。
まずは「視界に入るものを減らす」ことから始めてみましょう。
出しっぱなしのものを箱にまとめるだけでもOK。
完璧に片づける必要はありません。
「何も考えなくていい空間」をひとつでも作ることが、心をふっと軽くしてくれます。
リセットされた空間は、心のリセットにもつながります。
家を“居場所”に変える小さな工夫が、日々の疲れに効いてくるんです。
一日中“オン”になっていませんか?
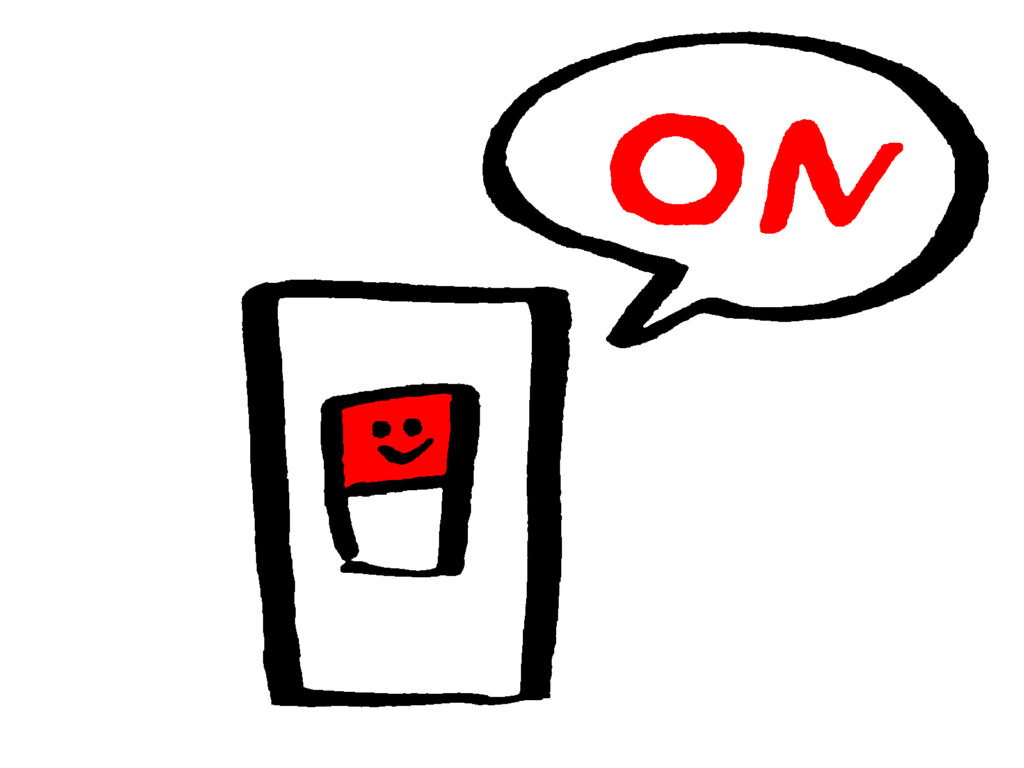
家にいるのに、なぜかリラックスできない。
休んでいるつもりなのに、心がざわざわして落ち着かない――。
そんなとき、自分の「オンとオフのスイッチ」が壊れかけていることに気づいていますか?
現代の暮らしは、“常に接続されている”状態が当たり前。
通知音が鳴るたびにスマホを確認し、仕事やSNSの返信を考えて、意識が外に向いたまま。
これでは家にいても、ずっと「オンモード」のままになってしまいます。
また、在宅ワークが増えた今、「家=職場」という感覚になっている人も多いでしょう。
これにより、本来オフになるべき空間で、気持ちが切り替わらない状態が続き、心がずっと緊張しっぱなしになってしまうんです。
そんな時は、自分の中で「ここからはオフ」というルールを作ることが大切です。
たとえば、部屋着に着替える・部屋の照明を落とす・お気に入りの香りを焚く――。
小さなことでも構いません。
“意図的な切り替え行動”が、脳に「もう休んでいいよ」と伝えてくれるのです。
一日中「オン」のままだと、心も体もどこかでパンクしてしまいます。
暮らしの中に“スイッチを切る瞬間”をつくること。
それが、家にいながら元気を取り戻す秘訣になります。
音と光の刺激で、家が「休めない場所」に

テレビの音、スマホの通知音、冷蔵庫の稼働音――。
何気ない日常の“音”や、“まぶしすぎる照明”が、実はあなたの心と体を疲れさせている原因かもしれません。
常に何かが鳴っていたり、天井からの強い白色照明にさらされていたりすると、自律神経が常に緊張状態になってしまうのです。
特に、夜遅くまでスマホを見ていたり、部屋全体を明るくしすぎていたりすると、脳が「昼間だ」と錯覚してしまい、リラックスモードに入れません。
この状態が続くと、眠りが浅くなったり、翌日に疲れを持ち越したりしてしまいます。
心が本当に休まる環境をつくるには、「光と音の質」を見直すことが大切です。
具体的には、間接照明や暖色系のライトに切り替えたり、夜は無音か自然音のBGMで過ごしたりするのがおすすめ。
さらに、寝る1時間前からスマホやテレビの画面を見る時間を減らすことで、眠りの質も格段に上がります。
それが、家を「心から休める場所」に変える大きなポイントになります。
まとめ:暮らしの小さな見直しが、心の疲れを軽くする
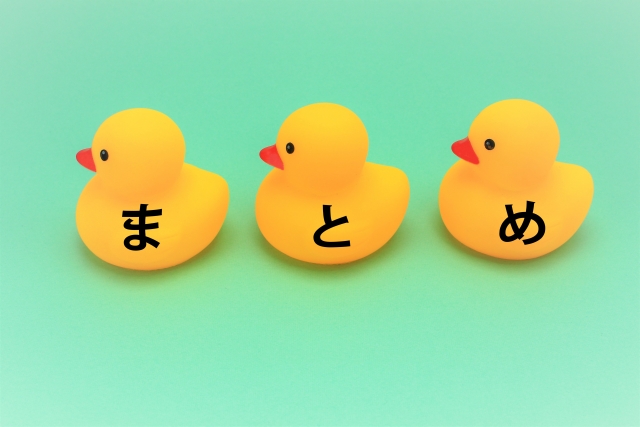
「家にいるのに疲れてしまう」――その原因は、外ではなく“暮らしの中”に潜んでいることが多いんです。
完璧主義、部屋の圧、一日中オンの状態、音と光の刺激…。
どれも一見するとささいなことのように思えますが、積み重なることで心のエネルギーをじわじわと奪っていきます。
でも逆に言えば、その“暮らしのクセ”をほんの少し見直すだけで、あなたの心はもっとラクになれるということでもあります。
完璧じゃなくていい。
余白があっていい。
切り替えが下手でもいい。
大切なのは、どうすれば、自分がホッとできるかを知ることです。
暮らしは、あなた自身を整えるための“土台”。
今日できる、小さな一歩から始めてみてください。
それだけでも、明日の自分がちょっと軽くなっているはずです。

草刈りの申し込みはこちら↑

インスタグラムはこちらから↑