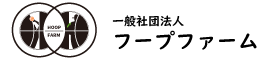寒くなる前にやっておきたい!冬じたくの習慣リスト
目次
はじめに|「冬じたく」ってなに?寒さに負けない暮らしの準備とは

気温が下がり始める秋の終わりから冬の初めにかけては、「冬じたく」のベストタイミングです。
「冬じたく」とは、ただ衣替えをするだけではありません。
暮らしの中で寒さをやわらげる工夫をしたり、健康管理や家のメンテナンスをしたりすることも含まれます。
たとえば、あたたかい毛布やこたつを出すタイミング、加湿器の準備、暖房機器の点検など。
どれも冬本番になってからでは遅れがちで、「あのときやっておけば…」と後悔することも少なくありません。
また、最近は電気代やガス代の高騰もあり、暖房コストを少しでも下げるために「早めの冬じたく」が注目されています。
カーテンの工夫や断熱グッズの活用など、ちょっとした準備が冬の快適さを大きく変えてくれるのです。
このコラムでは、寒さが本格化する前にやっておきたい「冬じたく」のポイントを、暮らしの場面ごとにわかりやすくご紹介します。
面倒そうに感じるかもしれませんが、少しずつでも始めておくことで、冬を安心して、そして心地よく過ごすことができるようになります。
衣替えだけじゃない!服・寝具・あったかアイテムの見直し

冬じたくの第一歩は、「身につけるもの」「身を守るもの」の見直しから始めるのがおすすめです。
衣替えはもちろんのこと、冬の生活を快適にするためには、服や寝具、あったかグッズの見直しも欠かせません。
まず衣類について。
肌寒くなってから慌てないために、コートやダウン、ニット、インナーなどを早めにチェックしておきましょう。
サイズが合っているか、虫食いなどの傷みがないか、クリーニングが必要かどうかも確認しておくと安心です。
さらに、インナーウェアは発熱素材や吸湿性のあるものを取り入れると、重ね着しすぎずスマートに温かさを確保できます。
次に寝具です。
掛け布団や毛布、敷きパッドなど、肌に触れる寝具は特に大切なアイテム。
冬用のあたたかい布団に切り替えるのはもちろんですが、電気毛布や湯たんぽなどの補助アイテムを使うことで、寝る前の寒さ対策もばっちりです。
布団のカバーやパッドは冬仕様に変えるだけで保温効果がアップするので、見直しをおすすめします。
また、家の中での寒さをやわらげる「あったかアイテム」も冬じたくには欠かせません。
ルームソックス、膝掛け、もこもこのルームウェア、ブランケット、こたつ、電気ストーブなどは、寒い日々に欠かせない存在。
買い替えのタイミングかどうかも含めて、いまのうちに点検しておくとよいでしょう。
これらの準備を早めに整えておくことで、冬の到来が少し楽しみになるかもしれません。
「備えあれば憂いなし」、あたたかな冬支度は、あなたと家族の心と体を守ってくれる頼もしい一歩です。
冷えを防ぐ!キッチン・お風呂・トイレの冬支度ポイント

家の中でも特に冷えやすい場所といえば、キッチン・お風呂・トイレ。
この3つは毎日使う場所だからこそ、冬じたくをしておくことで「寒っ!」というストレスをグッと減らせます。
冷気を遮る工夫や、ヒヤッとしない工夫をしておくと、冬の暮らしがグンと快適に。
キッチン
朝の料理中や洗い物のとき、冷たい水に手を入れるのがつらい…という経験、ありますよね。
そんなときは、食器洗い用にゴム手袋を用意しておくのがおすすめ。
さらに、足元の冷えを防ぐためにキッチンマットや小さなホットカーペットを敷くのも効果的です。
窓や換気扇から冷気が入るなら、すきまテープや断熱シートで寒さをブロックしましょう。
お風呂まわりも要チェック。
冬になると、脱衣所との温度差でヒートショックが心配になります。
脱衣所に小型ヒーターや暖房器具を設置したり、入浴前に浴室をシャワーであたためたりするのがおすすめ。
また、風呂のフタをこまめに使って湯冷めを防ぐことも重要です。
地味に寒いのがトイレ。
特に深夜や早朝に行くとき、冷えた便座に座るのはつらいもの。
暖房便座や便座カバーをつけるのはもちろん、トイレマットやスリッパを冬仕様に変えるだけでも冷え対策になります。
窓のあるトイレなら断熱カーテンやすきま風の対策も忘れずに。
こうした「毎日使う場所」にちょっと手を加えるだけで、冬の暮らしはグッとあたたかくなります。
寒さをガマンするのではなく、やさしくブロックする。そんな冬じたくを心がけてみましょう。
電気代が高くなる前に!暖房・節電・断熱の工夫

冬になるとグンと上がるのが、暖房費などの光熱費。
とはいえ、寒さをガマンして体調を崩すわけにもいかない…。
だからこそ、上手に「暖かさをキープしつつ節電」する工夫が大切です。
ポイントは、暖房の使い方を見直すことと、部屋全体の断熱性を高めること。
まず暖房器具は、使い方次第で消費電力が大きく変わります。
たとえばエアコンの場合、設定温度を「20〜22℃」にして、サーキュレーターや扇風機で空気を循環させると効率的。
こまめなオン・オフよりも、弱運転でつけっぱなしの方が電気代が安くなることもあります。
こたつや電気毛布を併用して、体をピンポイントで温めるのも効果的です。
節電のもう一つの鍵は「断熱」。
部屋に入ってくる冷気と、逃げていく暖気をブロックするだけで、暖房効率はぐんと上がります。
たとえば、窓に貼る断熱シートやカーテンの裏に仕込む保温ライナーは、手軽にできて効果大。
カーテンの裾が床に届くようにするのも冷気侵入を防ぎます。
ドアや窓のすきま風には、すきまテープやボードでの対策が有効。
さらに床の冷たさ対策も見逃せません。
ラグやカーペットの下にアルミシートを敷いたり、厚手の絨毯を使ったりすることで、下からの冷えを防げます。
足元が温まると、体感温度も上がるので暖房に頼りすぎなくても快適に。
「我慢して節電」ではなく、「仕組みで暖かさを逃がさない」工夫が、冬を快適に過ごすコツ。
電気代の請求書にドキッとしないためにも、今のうちからできる工夫を始めてみましょう。
乾燥・ウイルス対策に!加湿器と空気の整え術

冬が近づくと、空気の乾燥が気になりますよね。
肌のカサつきや喉のイガイガだけでなく、風邪やインフルエンザ、最近ではウイルス対策の面でも「湿度管理」はとても大切なポイント。
実は、湿度が40〜60%に保たれていると、ウイルスの生存率が下がるというデータもあります。
そこで活躍するのが加湿器。
特に寝室やリビングなど長時間過ごす部屋には、超音波式やスチーム式など用途に合った加湿器を導入すると◎。
最近ではアロマ対応のものも多く、リラックス効果もプラスできます。
ただし、水の入れっぱなしは雑菌の繁殖原因になるので、こまめなお手入れは忘れずに。
加湿器がなくてもできる乾燥対策もあります。
たとえば、濡れタオルを部屋に干す、やかんでお湯を沸かす、観葉植物を置くなども自然な加湿方法。
特に洗濯物の室内干しは、一石二鳥でおすすめ。湿度も上がって、衣類も早く乾きます。
また、空気清浄機も併用すると空気環境がより整います。
ホコリや花粉、PM2.5、ウイルスなどをフィルターで除去してくれるので、体調管理に効果的。
風邪をひきやすい人や小さなお子さんがいる家庭は、空気清浄+加湿のハイブリッドタイプも人気です。
空気と湿度をコントロールするだけで、冬の体調がかなり変わってきます。
家の中の「見えない空気」に少し意識を向けるだけで、心も体も過ごしやすくなりますよ。
6. 冬の食材を先取り!体を温める食材と常備リスト

冬の寒さに備えるなら、服や暖房だけでなく「食べもの」からの温活も欠かせません。
体の中からぽかぽか温まる食材を、今のうちから意識して取り入れるだけで、冷えにくい身体づくりができます。
体を温める代表的な食材には、根菜類や発酵食品、スパイス類があります。
たとえば、にんじん・ごぼう・大根などの根菜は、煮物や味噌汁にするだけでじんわり温まります。
また、生姜やにんにくは、血行を促進して冷えを和らげる力があります。
お味噌や納豆、甘酒などの発酵食品も、腸内環境を整えて体温アップにつながるのでおすすめです。
さらに、シナモンや黒胡椒などのスパイスも、少量でも体を温める作用があります。
紅茶に生姜やシナモンを加えた「ホットスパイスティー」なども、リラックスタイムにぴったりです。
常備しておくと便利な食材は、
- 冷蔵:白菜、ねぎ、小松菜、きのこ類、豆腐、納豆、味噌など
- 冷凍:ごぼう、里芋、かぼちゃ、根菜ミックス
- 常温保存:乾燥しいたけ、乾燥わかめ、生姜、にんにく、スパイス類、もち、切り干し大根など
特に冷凍の根菜ミックスやカット野菜は、忙しい日にもすぐ使えて、時短にもなります。
味噌汁や鍋料理、スープなどに加えれば、体も心もあたたまる冬のごちそうに。
「冬の準備=食材のストック」と考えて、少しずつ買い足していくと、冬本番も安心して乗り切れますよ。
7. まとめ|冬を快適に迎えるために、今できることから始めよう

冬じたくは「寒くなってから」ではなく、「寒くなる前に」始めるのがポイントです。
秋のうちに少しずつ準備を整えておけば、寒さが本格化しても慌てることなく、ぬくもりのある暮らしを楽しめます。
今回ご紹介した習慣は、どれも今日から少しずつ取り入れられるものばかり。
衣替えをしたり、寝具を整えたり、冷える場所をチェックしたり。
ちょっとした行動が、冬の快適さにつながります。
特に大切なのは、「心と体の冷え対策」
温かい服や食べ物で体を守ることはもちろん、気持ちの面でもホッとできる空間づくりが、冬のストレスを減らしてくれます。
あらかじめ冬に備えることで、「あれやっておけばよかった…」という後悔も減り、安心感を持って年末年始を迎えることができるでしょう。
忙しい日々の中でも、5分だけ冬のための行動を意識する。そんな小さな習慣が、やがて「冬を楽しむ余裕」につながります。
さあ、今年の冬は、自分にとって心地よい季節に変えていきましょう。

草刈りの申し込みはこちら↑

インスタグラムはこちらから↑